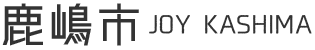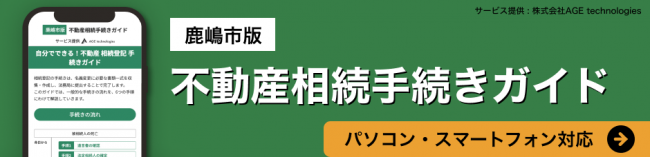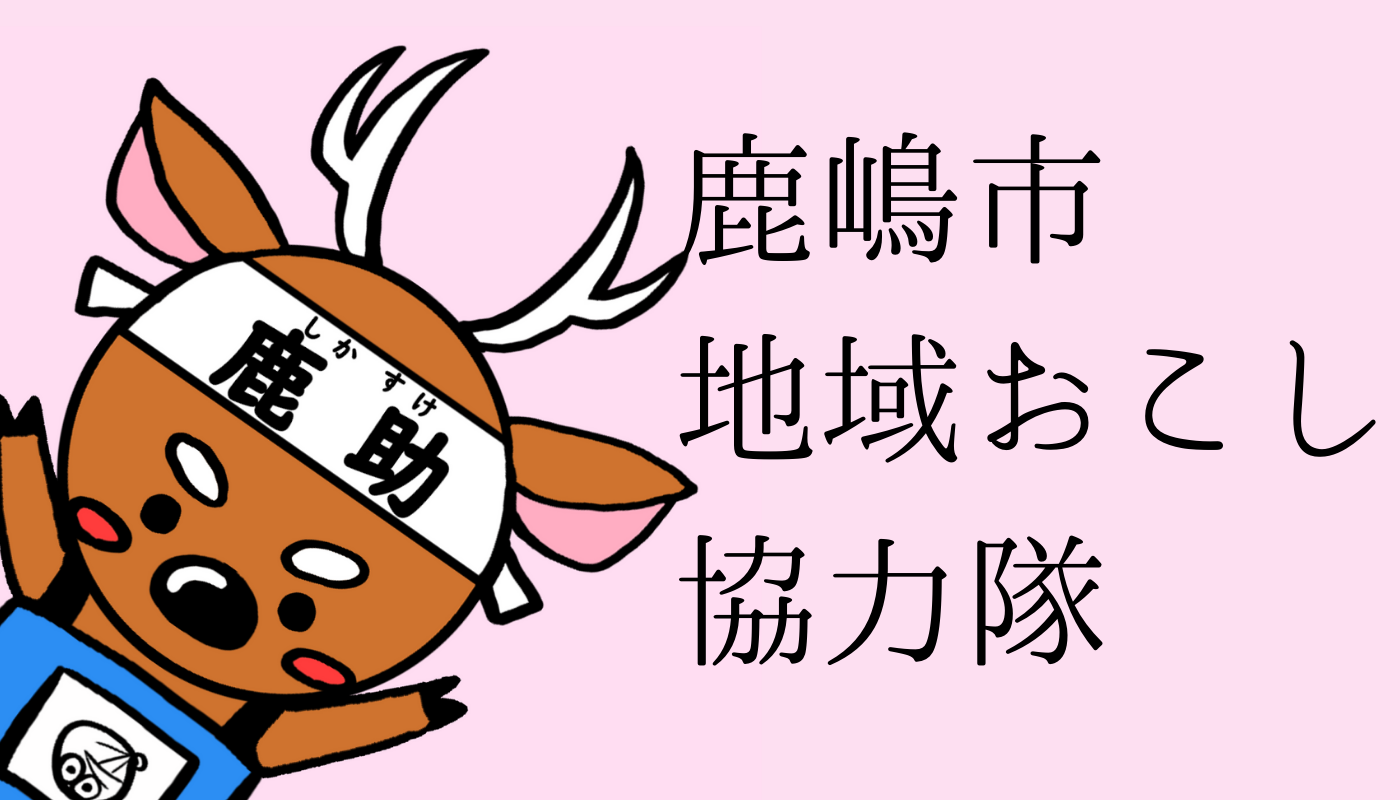※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
空家等の適正管理依頼の通知とは・・・
市では、空家等として通報、情報提供があった空家等の所有者等に対して、適正管理をお願いする通知を送付しています。
通知しようとする空家等の登記名義人が死亡しており、現在の管理者が確知できないとき、戸籍により法定相続人を調査し、特定した相続人に適正管理を依頼しています。
亡くなってから長期間経過している場合、相続人から見て親のおじおばなど、ほとんど面識のない親族からの相続について、突然自治体から連絡が来るといった事例も少なくありません。
身に覚えのない相続について連絡が来た場合、どのような対応が必要となるかを案内します。
家族や親戚等、他の法定相続人と思われる方への連絡、相談
同じ相続人の立場にある方はいないか、家族や親戚の方と相談してください。
空家等として通報、情報提供がある物件は、相続権を有する人物が多岐にわたる事例があります。家族や親戚と協力して事態の把握に努めましょう。
法定相続人であるかの確認
法定相続人となる人について
1.相続順位
相続が発生したとき、次の順番で相続人になります。
|
第1順位 |
子(直系卑属) |
|
第2順位 |
親(直系尊属) |
|
第3順位 |
兄弟姉妹 |
前順位者の相続人が一人もいない場合、前順位者の全員が相続放棄した場合、次順位者が相続人となります。
また、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者の有無にかかわらず、上記の者も順に相続人となります。
2.数次相続
被相続人が死亡後(一次相続)、遺産分割協議や移転登記、名義変更等が済まないうちに、相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が開始され、相続人の相続権を承継(相続)すること
3.代襲相続
相続人となるべき子又は兄弟姉妹が一定の事由(相続開始以前の死亡など)により相続権を失った場合には、その者(被代襲者)の子がその者の受けるはずだった相続分を被相続人から直接相続すること
被代襲者:被相続人の子(直系卑属)または兄弟姉妹
※被代襲者(相続人となるべき者)の相続開始以前の死亡、相続欠格や廃除による相続権の喪失が代襲相続の発生要因となる。
※相続放棄をした場合、相続放棄は代襲原因とならないため、相続放棄した者の直系卑属は代襲相続が認められていない。
再代襲:被代襲者の子も代襲相続権を失った場合には、被代襲者の子の直系卑属が代襲相続すること
※被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合は再代襲はない。(被相続人の甥・姪)まで
相続の承認又は放棄
相続を承認するか放棄するかは相続人が選択できますが、限定承認または相続放棄を行う場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きが必要です。
1.単純承認
被相続人の相続財産を無条件で相続すること
※単純承認すると、その相続人は、被相続人の資産だけでなく、負債もすべて継承する。
法定単純承認:相続人が相続財産を処分した場合や、相続開始を知った時から原則3か月以内(熟慮期間)に相続放棄又は限定承認の手続きを行わない場合、単純承認したものとして扱われる制度のこと
※法定単純承認が成立すると、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなる。
2.限定承認
相続によって得た資産の範囲で被相続人の負っていた負債または遺贈を共済し、財産が残ればそれを相続する相続方法のこと
※相続した資産の範囲内で負債を弁済すればよいため、相続人自身の財産まで弁済にあてる必要ない。相続開始を知った時から3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てることが必要となる。
3.相続放棄
相続開始により一応生じた相続の効果を、全面的・確定的に消滅させる行為のこと
※相続放棄は、熟慮期間内(自己にために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に家庭裁判所に申述を行い、家庭裁判所が受理することによって効力を生じる。
相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる
※相続放棄は代襲原因ではないので、放棄者の子は放棄者を代襲して相続することはできない。
【期間の伸長の申立て】
相続の承認又は放棄の期限は、相続の開始があったことを知った時から3か月ですが、3か月調査を行ってもなお、相続を承認するか放棄するか判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所に行うことで、期間を伸ばすことができます。
相続するかしないかの判断にあたって(財産等の調査)
1.家屋、土地
法務局にて登記事項証明書を取得することで、その不動産の地積等の概要や共有者の有無、抵当権の有無などの確認ができます。
土地の価値については、公表されている相続税路線価や地価公示を参照することで、おおよその目安がわかります。
2.他の財産の調査
3.税や保険料の滞納の確認
4.その他の債務
専門家への相談
1.弁護士会に相談 茨城県弁護士会 水戸市大町2-2-75 (029-221-3501)
2.司法書士に相談 茨城司法書士会 水戸市五軒町1-3-16 (029-225-0111)
3.通知送付元の自治体に相談
4.法テラス 国が設置した法テラスでは、相談窓口等の紹介を行っています。
相続手続きのガイドページについて
次のページでは、不動産相続登記についてわかりやすく解説しています。
不動産を相続したら、このページを参考に手続きを行ってみましょう。